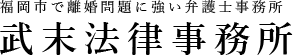- HOME>
- 知的財産権トラブル
基礎知識
仮処分・物件目録
- 今、知財訴訟に先立って、仮処分が用いられることは少なくなりました。
- しかし、私が、弁護士になって間もない頃(昭和50年頃)は、地方特に支部あたりでは、通常の事件と同じ よ うに、申立人側の審問だけで、決定がなされていました。従って、慣れた弁護士は可能な限り、地方の支部を管轄にして申立を行っていました。
- しかし、特許等の知財事件の判断は複雑困難で、かつ知財が絡む商品は企業の有力商品であることが多いので、安易に仮処分がなされたら、企業にとって倒産の危機や取り返しのつかない莫大な損害を被ることとなります。
- そこで、最高裁判所が、仮処分は本案訴訟と同じ審理を行うべしと指導したため、仮処分を起こしても、本訴の結果待ちとされ、結局取下げを促されて、相手方から逆宣伝に用いられるということになって、誰も最初から仮処分をかけ なくなったものと認めれます。
- 但し、例外が有ります。判決も出ていないのに、相手が特許等を侵害していると取引先等に吹聴する行為に対しては営業妨害の仮処分が直ぐに出ます。
知財権利の有効無効の判断や侵害の範囲の判断には専門的な判断を要することと、大抵の場合、無智による思い込みをしている場合が多く、相手方に事実上不当な損害を与えるからですが、それに対して権利を吹聴する側には緊急を要する実害が少ないと認められるからです。 - また、最高裁判所が、仮処分が取り消された場合には、申請者の過失が推定されるという原則を示したので(昭和43年12月14日判決)、不当な仮処分による損害賠償請求をされ易くなったというのも安易に仮処分を申立なくなった原因があるかも知れません。
この法理は、直接本訴を起こしながら相手に営業妨害行為を繰り返す原告において、訴訟指揮のなかで理由がないことが事実上判断された後の行為は、過失や故意を認められる可能性があることを示しているものと解釈されます。 - 私が、昭和58年に、九州に帰ってきた頃に、佐世保支部で、特許侵害主張事件で審問なしの仮処分決定がなされ、しかも物件目録における対象物件の特定が、具体的な物品の物件目録ではなく、特許申請書の添付図面の写しを物件目録として、物件の特定がなされていました。
執行官もこの図面により執行していましたが、あきれる事態でした。特許侵害の有無の判断のような微妙な専門的かつ法律的判断を要する物件の特定と表示を、裁判官がなしておらず、従って執行官が対象物件の特定判断を、事実上、してしまっていたからです。
債務者の相談を受けた当職は、すぐに執行管轄の福岡地裁に対して異議申立をし、まじめな裁判官の求めに応じて、事実上仮処分が解除される内容の和解で解決しました。本来なら、先例集に記録を残したかったのですが、担当の裁判官の正確な認識と正直な対応が良かったことと、仮処分を下した若い裁判官の将来を考慮したからです。
均等論
- 均等論とは、特許発明の権利範囲の判断基準を、請求の範囲記載とおりにいわば形式的に解釈する考え方に対峙する考え方で、判断基準である請求の範囲の記載のなかで本質的部分と非本質的部分に分けて、本質的部分を重視して解釈するという考え方です。
- 現在は、特許発明の権利範囲の判断基準に均等論を用いることは自明の理となっていますが、私が水田耕一法律特許事務所で教授を受けていたころは、特許法解釈の一大論争点でした。
裁判所の判断にも統一されたものがなく、関東管内では、Mというカリスマ的な裁判官の指導で、均等論は否定されており、他方関西管内では物事を実質的に考える伝統からか均等論が採用されており、全く同じ内容の事件が、大阪では勝訴し(侵害差し止め側ないし権利無効主張側)、東京では敗訴する(被差止側ないし権利有効主張側)という現象が事実として起こっており、それぞれの立場で、先に有利な管轄で訴訟を提起するということが、まじめに検討されていました。
- 九州では、特許訴訟の経験が乏しいうえに、東京の先例を重視する傾向がありましたので、均等論の主張は殆ど無視される傾向にありました。
- 平成10年に至り、最高裁判所が均等論を前提とした画期的な判断をして以来、全ての知的財産権の解釈が実質的になされるようになったと理解されます。
- その後、均等論に法的根拠を与えるべく、特許法第70条に2項が加えられ、長年に渡って築かれた判例法が立法化され、現在に至っています。
無効な登録権利に基づく侵害差止訴訟
- かっては、審判系訴訟に限らず、侵害系訴訟においても、裁判所が特許の有効性や権利範囲の判断するにあたって、特許庁の判断に委ねられていました。
その理由は、立法による分権制度があり、特許等の知財事件は高度に専門的な知識を要し、裁判官の知識では容易には判断できないということであり、加えて訴訟においても裁判に専門家である特許庁の調査官が補佐として付けられ、助言されるようになっていました。 - しかし、法律解釈の訓練を受けていた駆け出しの当職や知財に興味のある弁護士や裁判官等にとっては、理解しがたい判示内容や理由も少なくありませんでした。
その原因は、権利申請手続きが、申請者の提供する資料のみに基づいてなされ、利害関係人の意見や情報の提供を受けることなくなされる行政処分であるという制度からくるもので、立法趣旨に基づいた法解釈判断とは異なるという建前があったからと認められます。 - しかも、特許庁の無効審判事件は時間がかかり、かつ登録有効の審決が出され裁判所がその結果を踏まえて判決しても、その後審決取消訴訟で登録無効とされることが少なくなく、その関係の解決に解釈上複雑な解釈が求められました。
しかしこの35年の間に、法律解釈に基づいて社会的常識に近い判断をする先例が少しづつ現れ、本項で掲げる登録された権利が無効と判断される場合には特許庁の審判を待たないで、裁判所が無効であると判断出来ることなどが、最高裁判所で示され(判例変更)、それをもとに法律が改正されて現在に至っているものです。 - ただ、商標等の登録権利は、権利関係の安定のために、無効審判請求の除斥期間が定められているので、本来無効であるべき商標が、多く登録されたまま残存しており、これに基づいて権利行使しようとする者が少なくありません。
これに対して、法は、無効な権利に基づいて正当な権利行使を妨げられることがないように、登録無効要件と同じ要件を更に緩和させた要件をもって、使用する者を保護する救済規定を設けていますが、裁判所は、解釈論において、商標として保護すべき要部がない登録商標として、あるいは対象とされている使用標章に商標を侵害すべき要部が無いとして、商標としての類似性がないものとし、権利行使を認めていないので、被告側の代理人がしっかりとした抗弁をすれば、実害は有りません。
なお、無効な登録権利に基づいた、標章使用者に対する、営業妨害行為に対しては、不正競争防止法や民法(不法行為)により、差止や損害賠償の請求が認められますので、同知財の知識が普遍化すれば、社会問題化を防ぐことが可能であると思慮されます。 - 最近、特許庁で登録されている特許や商標等の登録権利が裁判所で無効とされる例が目立ちます。それは、従来特許庁は申請者に権利を付与するという行政処分的性格を有し法的特に専門的な法解釈を厳格に行わなかったからだと思慮されます。
これに対して、特許や商標等の権利侵害の判断のみならず権利の有効性の判断も権利が付与された法律の解釈や客観的な証拠判断に沿ってなすべきであるという当然の社会的ニーズに沿って、裁判所が法的解釈による判断を行ってきたので、その結果、登録権利が無効であるとされる裁判例が増えていると思慮されます。しかし、上記のとおり除斥期間内に訴訟にならないと登録権利の有効無効性が顕在化せずに、多くの無効原因を有して使用者を差止できない登録権利が多く存在するという不思議な現象が無くなるに至っていなのが現状です。 - 現在、知財部の事件は原告の勝訴率が低いと言われていますが、知財部先例をみていても、その判断理由に登録権利無効とされる場合が結構多いことが認められます。また、提訴に当たって、原告においては、申請専門家(特許庁対応)の弁理士の主導による、従って、実質的に判例法の理解に至っていない経験が少ない弁護士が関与するケースが多いことなどが考えられます。