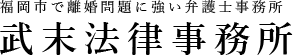- HOME>
- 子の監護者指定・引き渡し
監護者とは?親権で揉めた時、当面の監護権を決める必要性

親権と監護権を分けないのが、裁判所の立場です。しかし、離婚に至らない場合、子の身分上の法的決定や財産管理を認められる親権は両親双方に存在し、世話(監護)も両親が行います。
しかし、両親が別居し、離婚が成立するまでの間、いずれが子供と同居して世話(監護)をするかについて、争いがある場合、これを片方に決める必要性があります。事実上、双方監護は困難だからです。
子の監護者指定・引き渡しとは?家庭裁判所がどちらかの親を監護者に指定
別居に際し、片方の親がもう片方の親の承諾なしに子供を連れて別居する場合があります。
こうした時、もう片方の親(通常母親)は、それが子供の福祉に添わないと考える場合(現実には、子供可愛さが動機と認められる場合も少なくない)、子供の引き渡しを求めて家庭裁判所へ“子の監護者指定・引き渡し調停(合意に至らなければ審判に移行する)”を申し立てなければなりません。1年以上の時期が立つと、現状維持の原則が働いて、よほど子の福祉に反しない限り、子を引き取れなくなり、離婚に際し、必然的に親権が相手方に決められてしまうからです。
申立を受けて裁判所は、子供の福祉を考えた時、どちらの親が監護者になった方が良いかを検討し、書類等で完全に立証されない場合でも、裁判所の調査官による調査により、子の福祉に添うと判断される親を離婚成立までの間の監護者に指定し、子供の引き渡しの審判を下します。通常は、裁判所の説得を受けて(裁判所は、子の福祉の観点から、なるべく合意に至るように努力します)、子を引き渡す事例が多くみられます。
しかし、相手方が、審判に従わなかった場合、間接強制(高額の金員の支払いを命じる)を命じたり、強制執行を命じ、その場合、子供が10歳程度以上であれば、執行官は嫌がるこどもを無理に執行することは為されないようですが、子供が低学年以下であれば、子供が抵抗しても執行官が強制的に執行します。
また、離婚時の親権は、子の監護者の指定調停や審判時の判断に基づいて、定められるのが通常なので、放置しないことです。また、まれに、監護者が精神的な理由で入院したというような事情の変更により、異なった判断が、後に下されることもあります。
具体的事例(判例)に基づく子の引渡し強制執行の解説
仮処分の可否
離婚前に、父親が、子共を連れて、別居に至った場合に、母親が、仮の、子の監護者の指定と引き渡しを求めた事案で、審判前の保全処分を認めた東京家裁の平成28年4月7日審判を覆して、仮処分審判は原則として認められないという決定を、東京高裁が平成28年6月10日に出しました。
この傾向は、従来の先例において、認められてきたことですが、家裁が、容易に仮処分を認めたので、高裁において再確認されたものです。
母親から見れば、子の連れ去りが為されて1年位経ってからだと、現状優先の原則が働き、回復は困難となりますが、比較的速やかに(1~2カ月以内程度)、家庭裁判所に、子の監護者の指定と子の引渡の調停(審判)を求めれば、母親優先の原則の事情が存在する限り、現状優先の原則は働かないので、通常の場合、慌てることはありません。
このような事案で、通常の場合ではないとして、保全処分が認められるのは、子の連れ去りが強奪やそれに準じたものである場合や虐待の可能性が見込まれる場合や急激な環境の変化により子の健康状態の悪化が見込まれる場合等に限られます(その場合には母親の連れ去りに対しても同じことです)。なぜならば、通常の場合、子の監護者を定める場合には、慎重な調査や審理を経て行われるべき微妙なものであることで、仮の審理には適さないものであることや、仮処分には強制執行力が与えられますので、その後の慎重な判断を待って為すべきことが、安易に実行されると、子に与える打撃が大きいためということです。
通常の親子関係のもとでの(虐待歴がある等の場合ではなく)、父親に依る子の連れ去りに対しては、母親は、速やかに子の監護者の指定と引き渡しを求める調停を起こせば、調査官調査が為され、その結果に従った調停ないし審判が為されますので、心配することはありません
強制執行と子供の意思
最高裁判所第1小法廷平成24年(許)第48号間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件同25年3月28日決定で、給付の特定に欠けることがない場合に間接強制決定ができる旨示し、さらに、同事案は子供が執行を拒絶する意思を示した事案でしたが、判示は、審判がある以上、これの間接強制を妨げる理由にはならないとしました。その理由として、子の面会交流に係る審判は、子の心情等を踏まえたうえでされていることを掲げています。すなわち、調査官調査等によって試行面会や子の身上調査が為されていることの結果である点を重視して、当面の子の意思を真意なものとはとらえられない危惧を解消しています。しかし、子の意思の変化が、審判時とは異なる状況が生じたと言える時は、面会交流を禁止したり新たな条項を定める為の調停や審判申立てる理由となりうることに言及して、その解決方法を説示しています。
大阪家庭裁判所平成27年(家ロ)第50122号間接強制申立事件同28年2月1日決定は、未成年者が拒絶した事案で、債務者が未成年者に対して適切な指導助言することに依り、未成年者の福祉を害することなく義務を履行することが可能であるとして、間接強制を認めていますが、これは審判時における試行面会で債権者と子供が楽しそうに問題なく面会を行っていた等の実績を掲げており、事例決定(具体的な事例に即した判断で普遍的な基準を示したものではない)といえます。他方、東京家庭裁判所平成23年(ラ)第152号間接強制決定に対する執行抗告事件同23年3月23日決定は、子が債務者の説得にもかかわらず権利者の元に行く事を拒んだ事案で、義務者の義務は、権利者による子の引き渡しを妨害しないという不作為義務であるところ、義務者が子の引き渡しを妨害しているとも、その恐れがあるとも言えず、その立証も為されていないことを理由に、間接強制申立を却下しています。
従って、面会交流や引き渡しの調停や審判手続きにおいて、子が拒絶の意思を有している場合は(通常10歳前後以上はその意思が重視されます)、調査官調査により調査報告によりその意思が確認された段階で、面会交流や子の引渡を認めない判断が為されれば、執行するに至りませんが、仮に拒絶の意思の確認がない前提で審判が為されたとしても、義務者において執行を妨げる可能性が立証されない限り(執行に応じるように説得している限り)、間接強制は不可能ということになります。
権利者、義務者や裁判所が、子の意思を無視した義務を義務者に強いることは、仮にその内心が義務者に対する気遣いであったとしても、その自由意思を抑圧し、子の福祉に添わないことになるとした先例も存在します。
親権や監護権に基づく子の引渡しを実効するための強制執行について、かっては、手続法が存在しないとか性質上なじまないとかの理由で、間接強制のみが認められ、直接強制は認めない傾向にありましたが、近年は、民事執行法169条(動産執行)の類推適用により、直接執行を認める傾向に変わり、さらに国会において法律制定が検討されています。
しかし、最高裁判所第3小法廷平成30年(許)第13号間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件同31年4月26日決定は、妻の申立による家裁の引渡命令により家裁執行官が夫宅に出向いたが(直接強制)、9歳の長男は激しくこれに抵抗し引渡ができなかったため、妻が夫に制裁金(間接強制)を求めていた事案で、原決定を破棄し原々決定を取消して、同申立を却下しました。権利濫用として認めないという決定でした。これは、法律専門家によっては、例外的判決(決定)であると評するものもあります。子供の年齢が9歳であるのも、従来の基準(12歳くらい=中学生年齢)に比べ年少化したと評するものもあります。最近の子供は、小学校高学年においては、既にしっかりとした考えや判断力を有しており、子供であると侮ることは正しくないと思います。従って、最近の先例は10歳という基準を用いるケースも増えていました。しかし、小学校低学年においても、子供によってはしっかりとした判断力を有している子もいます。また、合理的判断によるものではなくても、親密な親子の絆に基づく心情をも含めて、当職は、子供の意思を尊重すべきであると考えています。
平成31年の最高裁判所決定は、東京家庭裁判所平成23年(ラ)第152号間接強制決定に対する執行抗告事件同23年3月23日決定が、子が債務者の説得にもかかわらず権利者の元に行く事を拒んだ事案で、義務者の義務は、権利者による子の引き渡しを妨害しないという不作為義務であるところ、義務者が子の引き渡しを妨害しているとも、その恐れがあるとも言えないとした発想と同趣旨と認められます。
この考え方を前提とすると、子の引渡は、親同士の関係ではなく、親と子の関係であると見るのが、本質的であるとの考えに至ります。従って、子が嫌がっているのに、親に対して強制執行をすることは、何の効果もないばかりか、子が執行を受ける親に気配りを強制されることになるので、まったく子の福祉に反する強制行動であるというべきことになります。言葉を変えると、監護親の義務は、相手の親に引き渡す義務ではなくて、引き渡しを妨げない義務に止まり、強制執行になじまないものという性質を有しています。
しかし、結果として、調査官による調査報告やこれに基づく裁判官による審判よりも、直近の家裁執行官の事実判断報告が、重要な機能役割を果たすことになるので、家裁執行官にはしっかりとした事実観察や判断能力が求められることになりまが、本来は、執行官の能力職責の範囲ではないので、例外的判決(決定)であると評される所以です。